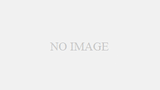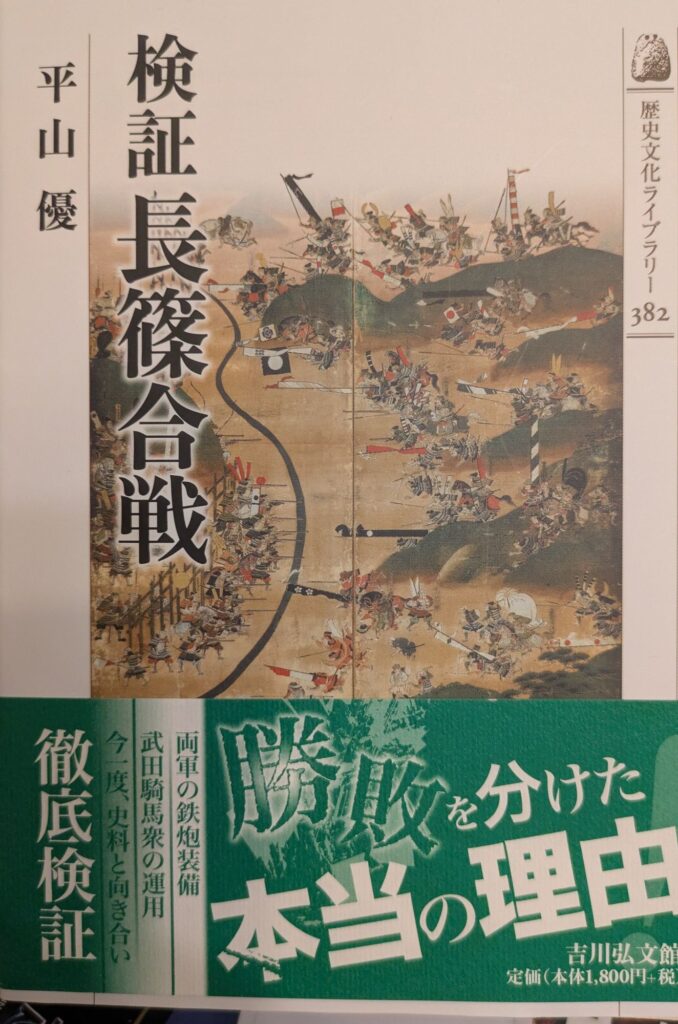
長篠の戦いというと、兵農分離により鍛えられた鉄砲の三段打ちと馬防柵による近代的な織田、徳川連合軍と、騎馬隊中心の古い戦い方の武田軍が戦い、見事に新しい方が勝利し、軍隊の戦い方の革新だ、と言うような、教科書等で示されたイメージが染み付いていると思いますが、どうやらそうではなさそうです。
まず、武田軍が鉄砲隊を軽視して、旧来からの騎馬隊での戦い方に固執した為に敗北したというイメージだが、そんなことはなく、武田勝頼の父、武田信玄の時代から、鉄砲隊は編成されており、隊の編成の仕方や戦い方は織田軍と代わりはなかったという。
また、馬防柵については、特にこの戦いで始まったものではなく、旧来から用いられていた方法という。また柵の破り方についても方法論があった。なので、この合戦に当たって、武田勝頼は突破する自信を見せていたようです。
兵農分離が進んだのは豊臣秀吉の時代で戦がなくなり、武士が官僚化していく過程であり、織田信長の段階では、武田氏の状況とそんなに変わりはないことも述べられています。鉄砲隊の三段打ちについても、鉄砲が戦国武将の間に広まった当初からあった手法であり、織田信長の発明ではなさそうです。
では、長篠の戦いの勝負を決めた要因は何だったのかというと、鉄砲と、その弾薬、兵力の調達能力の差だということだ。織田信長は畿内を抑え、貿易を含めた物流を抑えていた。その為、武田軍に打ち勝ったのだ。
納得感があった。織田と武田の対決のような物語としては面白くないのだけど、色んなエビデンスを提示してもらいながら、論理的に語られていて、とても楽しく読めた。リアル長篠合戦がここにある。
また戦国時代の組織とか、合戦の実際なども学べて、とても有意義な本だった。